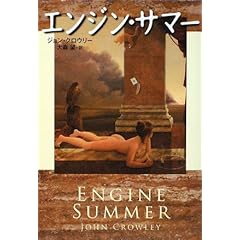
���ޡ�(ʸ����)���ɤߤޤ�����2008ǯ���������줿��ŵSF��
�줿1960ǯ��餷������ʸ�����Ǥ����λ���ο�����������������Τ褦�ʾ���Ǥ���
�������ﲼ�ζ�ĥ�θ��������̳����褬�����뤫�⤷��ʤ��Ȥ���������ä�60ǯ��ι�꤬���롢�����̣��̴���˾�⤢��㤷�ʤ��ǥ��ȥԥ�Ū�ӥ����ʤΤˡ��ʤ�����������ư���Ƥ��ޤ��ޤ����ɤΤ褦�ʾ����Ǥ���ʹ֤��Τ�ΤϤ��������Ѥ��ʤ��Ȥ������ۤ�����ޤ���
����21������Ω�����֤����ɤ�ȡ����������=�������(����)������Ū���ȻפäƤ����������¤Ϥ����Ǥ�ʤ��褦�ʤ�Τ⤢��ޤ������Ȥ��н���������ư��60��70ǯ��Ϥ������ä���Ǥ��礦�͡����Ϣ��Ū�ʹ��Ϣ����������������������������ư�����㤬ʸ����ݻ����褦��Ĺ���ˤ錄������������������������褦�ʵ��Ҥ�����ޤ��������ä�50ǯ�ǽ��������ࡼ�֥��ȤϱƤ����ĤäƤޤ��������ϸ�ѼԤ߰�Ƥ뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ��ä����Ǥ�60ǯ�������������ȿȤΥ��ȥ�å������Ԥ��������붵��ģ�Τ褦�˼��餬�Ҥ�٤��ʤ��Ƥ��ȿ���ݻ��Ǥ���ȻפäƤ��Τ����Τ�ޤ���
�ޤ������ܼ�����Ҷ��������ꤹ��褦���̤⤢��ޤ��������60ǯ��ˤ��꤬�����������ȥ�å����ä�̤������۶��Ǥϥ��ͤȤ�����ǰ��ɬ�פʤ��ʤä��Ȥ��Ƥ��뤷���ޥ͡��Ȥ�����ǰ��ɬ�װ��Ǥ��ä��ܼ�Ū�ʤ�ΤǤϤʤ��Ȥ������ۤǤ����Τ���ʸ�����Ǥ٤в�ʾ�ʤɰ�̣�Ϥʤ��ΤǤ��礦�͡�
�ܽ�����̤��ͤϡ���������⤿�餵�줿��ʪ���鿩�������Ƥ��ޤ����������ҳ�����˿���Φ����⤿�餵�줿���㥬���⡦�ȥ�����������ȥޥȡ���ɻҤʤɤǵ������ο����褬�礭���ƶ���Ϳ�����褦�ʤ�ΤʤΤǤ��礦�����������㥬����ϥ衼���åѤο����礭�����ä����ޤ������������ο�ʪ�Ϥ����ޤǤαƶ��ϤϤʤ��ä��褦�Ǥ����ष�������ο������Ȥ����������鱣ƿ����Ƥ��ޤ���
�ܽ�ˤϥ�ԥ奿�ȸƤФ�������礬�ФƤ��ޤ�����ʸ����ݻ����������οʹ֤�����Ǥ��ꡢ�ܽ�Υ��ȡ���ˤ����ƽ��פ��������ޤ������ʤ��Ȥ�2000ǯ�ʾ�ϱ�̿�����褦�Ǥ���
�ܽ�ϱѸ�Υ������Ȥ�����������ʸ������Τ���դ줿�������������ǿ��ɤߤ���ư㤦��̣�ǻȤ�줿�ꡢ�̤�ñ���ž�������ꤹ��Ȥ���������ˤʤäƤ���Τ������μ��Ͻ��פǤ���
�����ȥ�Υ��ޡ�(Engine summer)�⾮�����¤��̣���륤��ǥ����ޡ�(Indian summer)��ž���Ǥ��뤳�Ȥ��ż�����Ƥ��ޤ�����Ϥ䥤��ǥ�����Ȥ������դ��ؤ���ΤϾü��������������ƥ�������ϵ����ˤȤɤ���Ƥ��������Ǥϡ����Τ褦�ʸ��դ��Ѳ���������ΤǤ��礦��
�ǤӤ�ƻ�ɤ����Ȥ���������ǤӤ��ߤؤ�ƻ�Τ������ǰ��Ū�������֤����������¤λ��塣���줬�֥��ޡ��פ���������ʤΤǤ���
��ŵŪ����SF���⡣ʸ���ǤϿ����ˤʤäƥϡ��ɥ��С��Ǥ������֤褯�ʤäƤ��ޤ���






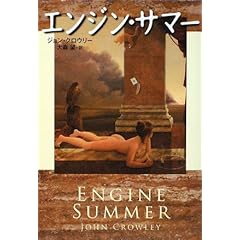



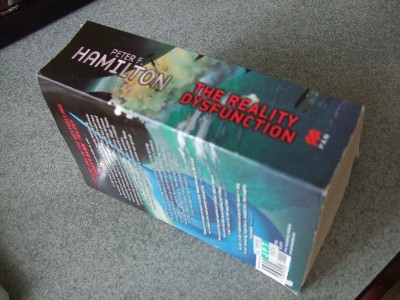











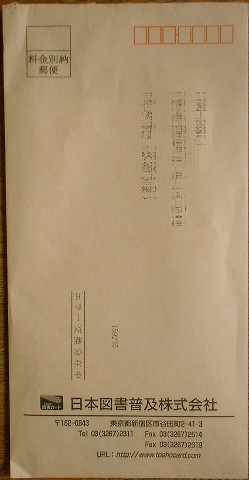
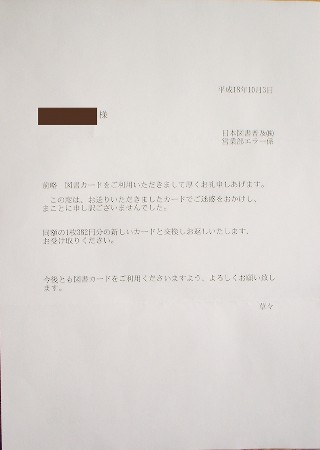


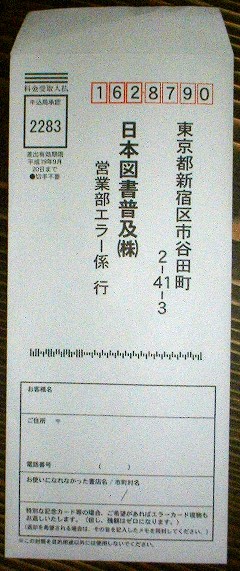












 ���ʤߤ�
���ʤߤ�







 �������ʸ���˺ܤäƤ�Ʀ�微�Τ���
�������ʸ���˺ܤäƤ�Ʀ�微�Τ���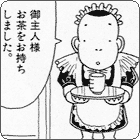 �긶�������Τ��߾���
�긶�������Τ��߾��� Ʀ����ľ����Ų�����
Ʀ����ľ����Ų����� Ʀ�微����ϻƻ��դ����
Ʀ�微����ϻƻ��դ����


